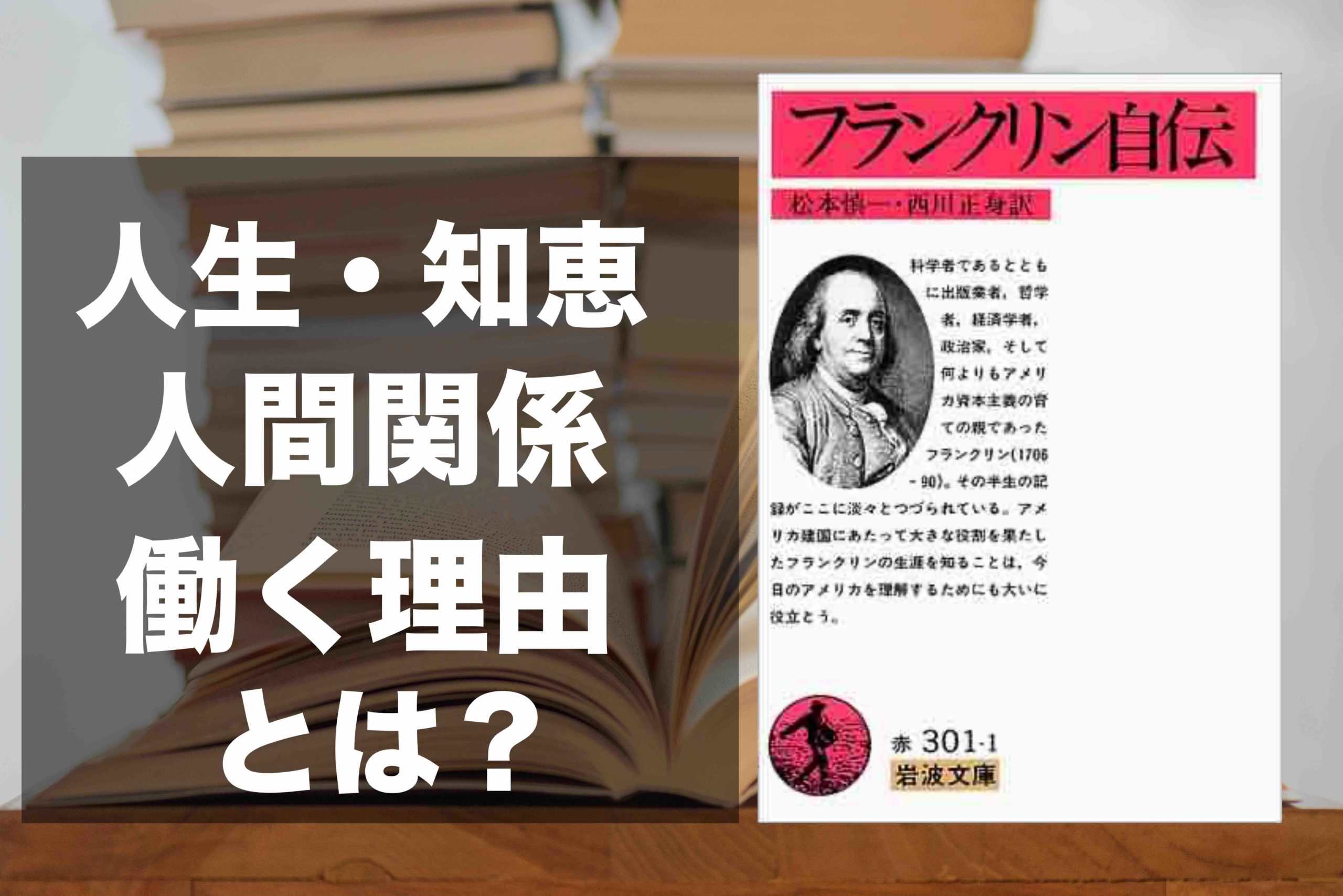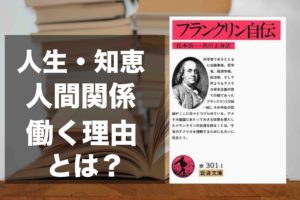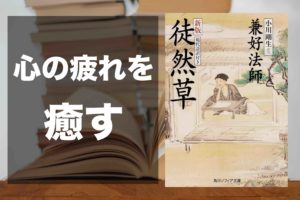こんにちは、masaです。
会社員しながら毎日読書してます。
今回の記事は、
- 『フランクリン自伝』が気になっている
- 『フランクリン自伝』からどんな学びが得られるのか知りたい
- 『フランクリン自伝』を読んだ個人の感想が聞きたい
という人におすすめの内容になっています。
フランクリン自伝があれば、自己啓発本のたぐいのものは必要ないです。
この本は自己啓発本ではありませんが、その役割を持っています。
そのくらい『フランクリン自伝』は、”思想うんぬん以上に現実的な行動が人生を好転させることができる”ということを教えてくれます。
『フランクリン自伝』はこんな人におすすめ
- これから人生を切り開いていきたい人
- 「アメリカ合衆国建国の父」と呼ばれる人物の生涯を知りたい人
- 節制と勤勉を身につけたい人
- 合理的に生きたい人
それでは、まずは『フランクリン自伝』がどんな本なのか説明していきます。
『フランクリン自伝』について
『フランクリン自伝』は、1771年から1790年の間に「アメリカ合衆国建国の父」と呼ばれたベンジャミン・フランクリンによって書かれました。
フランクリンの少年時代のことから書かれていて、失敗や成功の数々の経験から人生をどのように切り開いていったかが描かれています。
フランクリンは本書のはじめに、「私はいままでの生涯を初めからそのまま繰返すことに少しも依存はない」と言っており、自身の生涯を全肯定しています。
また、「私は多分大いに自分の自惚れをも満足させることだろう」「人生の他のさまざまな楽しみとともに、自惚れを与えて下さったことに対して神に感謝する」と言っており、本書の制作にも前向きだったことがうかがえます。
 masa
masaまさに「我が生涯に一片の悔いなし!」ですね。僕もそんなふうに言える人生を送りたい。。。
フランクリンについて


ベンジャミン・フランクリン(1706〜1790)は企業精神と公共の精神を発揮し、アメリカ合衆国の建国のために様々な貢献をしました。
その功績が社会に認められ、現在の米100ドル札に彼の肖像が描かれています。
フランクリンの功績を下記に示します。
- 印刷業で成功を収める
- アメリカ初の公共図書館を設立
- フィラデルフィアで郵便局長に就任
- アメリカ学術協会を設立
- フィラデルフィア・アカデミー(後のペンシルベニア大学)を創設
- 植民地の連合計画を提案
- 雷が電気であることを発見
- オックスフォード大学にて名誉学位を授与
- グラス・ハーモニカや燃焼効率の良いストーブを発明
- アメリカ合衆国の初代郵便局長に任命
- アメリカ独立宣言の起草委員になる
- アメリカ・スウェーデン友好通商条約を締結
- アメリカ独立を承認するパリ条約の使節団の一員として参加
主な功績だけでもこれだけあり、フランクリンが中心となってアメリカ独立のために大きな活躍をしたのかがわかります。



フランクリンのすごさを際立たせているのは、印刷業・政治家に加えて、科学者としても成果をあげているところですね
内容全体の雰囲気
先ほど述べましたが、フランクリンは本書の制作にあたって「自惚れを満足させる」と言っています。
しかし、本書の内容や文章自体は自慢や誇張が多く書かれているわけではなく、淡々と書かれています。
その理由は”読者に対して、自分の人生を自慢したいからではなく自分の人生から学びを得てほしいから”だと思います。
また、読者のためなるであろうところは丁寧に書かれており、読んでいて不快な印象を受けた箇所はほとんどありません。
そのほうが読者の腑に落ちやすいことをフランクリンは知っていたのだと思います。
人に物を教えようとする時に、押しの強い独断的な言い方で自分の考えを述べたのでは、人は反対したい気持ちになって素直には聞いてくれないだろう。
引用:フランクリン自伝
『フランクリン自伝』から得た学び
- 『十三徳』について
- 人との議論について
- 公共の精神について
- 人間が仕事をすべき理由
- 世の慣習よりも自分が正しいと思ったことに従う
『十三徳』について


『十三徳』は本書のメインともいえるポイントです。
『十三徳』とは、フランクリンがあらゆる本を読んで参考にしたり彼の経験によって考えられた13の徳のことです。
彼がどんなときにも過ちを犯さずに生活するために考案されました。
『十三徳』を身につけることができれば道徳的完成に到達することができるが、しかしそれは非常に困難な計画だとも言っています。
それは、何か過ちを犯さないように暮らしていると、思いもよらず他の過ちを犯してしまうことが多いからです。
『十三徳』を下記に示します。
第 一 節制 飽くほど食うなかれ。酔うまで飲むなかれ。
第 二 沈黙 自他に益なきことを語るなかれ。駄弁を弄するなかれ。
第 三 規律 物はすべて所を定めて置くべし。仕事はすべて時を定めてなすべし。
第 四 決断 なすべきことをなさんと決心すべし。決心したることは必ず実行すべし。
第 五 節約 自他に益なきことに金銭を費すなかれ。すなわち、浪費するなかれ。
第 六 勤勉 時間を空費するなかれ。つねに何か益あることに従うべし。無用の行いはすべて断つべし。
第 七 誠実 詐りを用いて人を害するなかれ。心事は無邪気に公正に保つべし。口に出だすこともまた然るべし。
第 八 正義 他人の利益を傷つけ、あるいは与うべきを与えずして人に損害を及ぼすべからず。
第 九 中庸 極端を避くべし。たとえ不法を受け、憤りに値すと思うとも、激怒を慎しむべし。
第 十 清潔 身体、衣服、住居に不潔を黙認すべからず。
第十一 平静 小事、日常茶飯事、または避けがたき出来事に平静を失うなかれ。
第十二 純潔 性交はもっぱら健康ないしは子孫のためにのみ行い、これに耽りて頭脳を鈍らせ、身体を弱め、または自他の平安ないし信用を傷つけるがごときことあるべからず。
第十三 謙譲 イエスおよびソクラテスに見習うべし。
引用:フランクリン自伝
フランクリンはこれらの徳を習得するために、下記の方法で取り組みました。
- 1週間で一つの項目に集中して取り組む
- 第一の項目から順番に行う
- 十三徳の手帳を作り、毎晩その日の過失を書き込む
- 13週間で全コースを1周し、1年に4回繰返す



1週間で一つだけならできそうですね
フランクリンはこの中でも『規律』を守るのが難しかったようです。
確かに時間を決めて行動するのはなかなか難しいですよね。僕はつい「もうちょっとだけ」とやりたいことを続けてしまったり、時間通りに仕事が終わらなかったりします。。。



フランクリンでも実践するのは難しかったんだなと思うと親近感が湧きます
学び
時間を決めて行動せよ
人との議論について


フランクリンは「人と議論をしすぎるのはよくない」と議論好きである自分自身を諫めています。
議論は、人と話し合うことで考察を深めたり人の意見を参考にして新たな発見が見つかるものですが、これが行きすぎてしまうと相手の意見に反対したり、相手を言い負かそうとしてしまうので相手に不快な印象を与えることになってしまいます。
幼いころから議論が好きなフランクリンは、議論に熱中するあまり相手を嫌な気分にさせてしまうことがしばしばあったようです。
この議論好きという性質はともすると非常に悪い癖になりやすいもので、この性質を実地に生かすとなると、どうしても人の言うことに反対せねばならず、そのためにしばしばきわめて人付きの悪い人間になり、こうして談話を不快なものにしたり、ぶちこわしたりしてしまうほかに、あるいは友情がえられるかも知れない場合にも不愉快な気持を起させ、恐らく敵意をさえ起させるのである。
引用:フランクリン自伝



人には『感情』があることを忘れてはいけません
学び
議論よりも大事なことがある
公共の精神について


フランクリンは、燃焼効率の良いストーブを開発し、人々の暮らしに貢献しました。
このとき特許を得ることができましたが、彼はあえてそれをしませんでした。
フランクリンは争いごとを好まず、自分だけ儲けようとせずに、人の役に立つことを喜びとしていたからです。
こういった公共の精神を、僕たちは学ぶべきです。
われわれは他人の発明から多大の利益を受けているのだから、自分が何か発明した場合にも、そのため人の役に立つのを喜ぶべきで、それを決して惜しむことがあってはならないという考えである。
引用:フランクリン自伝
学び
人の役に立つ喜びこそ、一番の利益である。
人間が仕事をすべき理由


本書では頻繁に『働くことの大切さ』について語られています。
フランクリンは、人が勤勉になると多くのものが得られると彼の経験から教えてくれます。
- 信用が得られる
- 勤勉かつ節制していれば貧しくなることはない
- スキルが身につく
- 仕事の後のご飯はおいしい
- 周りの人が手助けしてくれる
- いい出会いがある
人間は何かやっている時が一番満足しているものである。というのは、仕事をした日には彼らは素直で快活で、昼間よく働いたと思うものだから、晩は楽しく過すのであったが、仕事が休みの日にはとかく逆らいがちで喧嘩っぽく、豚肉やパンや何かに文句をつけ、終日不機嫌でいるのだった。それで私はある船長のことを思い出したのである。彼は部下の者にたえず仕事をあてがっておくことにしていた。ある時航海士がやってきて、仕事はすっかりすんで、もう何もさせることがないと告げると、彼は言ったものである。
「では錨を磨かせるがいい」
引用:フランクリン自伝



ブラックな環境は論外ですが、働くことに対してポジティブになれます
学び
働くことは、お金を得る以外にもいいことがたくさんある。
世の慣習よりも自分が正しいと思ったことに従う


少年時代、フランクリンの家では毎週日曜日になると教会で礼拝を行う習慣がありました。
しかし、フランクリンは文章を書く練習や読書がしたかったので礼拝にはなるべく参加しませんでした。
父親からは礼拝に参加するように何度も言われたようですが、それでも自分のやりたいことを優先しました。
フランクリンは幼い頃から、自分の時間の使い方を大切にしていたようです。
こうした練習や読書にあてた時間は、夜、仕事がすんだあとか、朝、仕事がはじまる前か、あるいは日曜日だったが、日曜日にはなんとか口実を作ってはひとり印刷所に残るようにして、みんなと一緒に礼拝に出かけるのをできるだけ避けた。
引用:フランクリン自伝



時間を有意義に使うなら、自分の都合を優先してもかまいません
学び
自分の時間を一番大切に使う。
その他の学び
フランクリン自伝は、今回紹介したこと以外にも、学べることがたくさんあります。
- 交渉術
- 宗教について
- 結婚について
- 良い人間関係の築き方
- お金の使い方
- 失敗談
現代社会でも通じることがたくさん書かれています。
最初にお伝えしましたが、この本があれば他の自己啓発本は必要ありません。
この本を読み終えた人なら自分のやるべきことがわかるはずです。
気になった人はぜひ手に取って読んでみてください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
電子書籍をたくさん読むならkindle unlimitedがおすすめです!
ビジネス書、小説、雑誌、マンガなど幅広いジャンルから選べて、200万冊以上が読み放題です。
初めての方は30日間無料で、いつでもキャンセルできます。
無料期間終了後は月980円で、月に1冊以上読めば余裕で元が取れちゃいます!